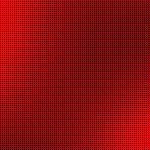企業の財務担当者の悩みのタネとなる資金繰り
企業の財務担当者の悩みのタネは、毎月の資金繰りをいかにして対応するかということに尽きます。
給料支払いが25日だとして債権が現金化されるのが月末だとしましょう。
資金化されるまでのギャップが一週間程度ありますから、金融機関から別途に資金調達を行うか、営業債権の現金化(受取手形を割引くか、電子債権をファクタリング割引するかといった方策)を行うかの選択を迫られることになります。
個人経営の小さな企業ですと、資金繰りの判断は社長や社長の奥さんが行うもの、ということになるかと思いますが、ある程度の規模の企業になりますと、月末の資金繰りの対策会議等を開催し対応を協議している会社も多いのではないでしょうか。
実際に私が勤務している企業においては私は金融面での資金調達担当者の役割を担っていますから、毎月20日前後に月末をどのように乗り切るかというテーマで資金繰りの会議を開催しています。
資金繰りは会社経営の生命線ともいえるのですが、20日に月末をどう乗り切るかを話し合うのは少し遅い気がします。
月初において大掴みでラフな形で会議を行い、20日には確認の意味で詳細をチェックするというように会議を回していけばよいのではと考えています。
資金調達を行う担当者にとって重要な関心事は適用金利がいくらになるのかということに尽きると考えます。
ファクタリングの割引レートは短期プライムレートが適用されるケースが多いと思うのですが、ファクタリング会社も競争社会ですから金利を弾力的に運用しようと考える会社も出てきているのでファクタリング会社を乗り換えても良いと考えるようになりました。
短期的な資金調達の方策としては金融機関に手形を差し入れたうえで資金を借り入れる手形貸付があります。
賞与資金や納税資金は返済期間が6か月というように定め、分割して返済していくケースも多いようです。
TIBORの適用について
またビジネス用のカードローン口座を設定するケースもありますが、このカードローンの方式は各都道府県に設置されている信用保証協会が保証しての借入スタイルが多いと感じますが、金利とは別に信用保証料が徴求されるので、トータルコストとしての金利としては少し高上りになるのではないでしょうか。
私が勤務している会社では、当座貸越契約を各金融機関と締結していまして、その適用金利はすべてが1%を切っている状態となっています。
これはやはり、マイナス金利の影響だと思いますが、金利の計算方法も東京インターバンクレート(TIBOR)という金利がベースとなっていて、借入期間に応じて適用金利が決定されるというスタイルをとっています。
TIBORの適用は中小企業ではあまり一般的ではないように感じられます。
逆にいえば、金融機関の側からすればTIBORを適用することで取引企業の経営内容を高く評価している、他行に取引が流出することを防ごうとしている姿勢がうかがえると考えます。

そんなわけで短期的な資金需要に対応するための融資は色々とあるのですが、融資金を借りる立場からすれば、財布をいくつも持つということになるということになります。
借りた場合は必ず返済しなければなりませんから、できるだけ金利の安い銀行から調達を埋めていくのが筋だと思うので、このセオリーを徹底的に貫いていくことは財務担当者の宿命だと考えて差し支えありません。
資金繰りを行っていくうえで議論されることは、必要な分を必要なだけ調達してくればよいという考えと月商1か月分ぐらいは預金口座に預金として持っているという考えがぶつかることになると思います。
結論からいえば必要な分だけを調達してくるという考えは非常に危険だと考えます。
お金のことであまり悩まずに経営するためには?
ファクタリングしてくるにも、当座貸越から調達するのにも日数はかかりますから、計算間違え等の不測の事態には対応できないので資金ショートを起こす懸念があるのです。
また必要な分だけ調達してくるという手法は財務分析上では経常収支比率の悪化と言う事態を招くことにもなります。
経常収支比率とは売上高を現金での収支に置き換えた経常収入と経費についても現金での支出に置き換えた経常支出で割った数値ということになります。
経常収支比率は100%超となることが一般的でして、100%割れが一時的なものでなく恒常的になってきますと金融機関としては警戒を始めることになります。
いわゆる黒字倒産、勘定合って銭足らずという状態は避けなければならないという考えが金融機関の中には少なからずあり、銀行での中小企業の経営をチェックしていくうえでの重要チェック項目にもなっているのです。
経常収支比率を安定的に100%以上とすることは財務担当者の使命であるようにも思います。
そのためには月商1か月分の預金残高をもつというセオリーはセオリー中のセオリーとでもいうべきものだと考えます。
資金を豊富に持ち、お金のことであまり悩まずに経営していきたいものです。
関連記事
最終更新日 2025年7月7日